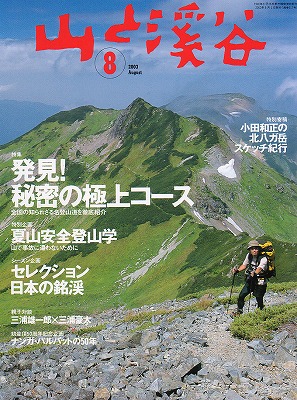 北穂池は、北穂高岳の東面にたたずむ小さな池である。そこへ行くには、一般縦走路を外れて険しい岩場を下っていかなければならない。よって誰もが容易に行けるというわけではなく、訪れる登山者もほとんどいない。
北穂池は、北穂高岳の東面にたたずむ小さな池である。そこへ行くには、一般縦走路を外れて険しい岩場を下っていかなければならない。よって誰もが容易に行けるというわけではなく、訪れる登山者もほとんどいない。藤本勇さん(66歳・当時)にとって、北穂池は「ぜひ一度訪れてみたい」と思っていた場所だった。というのも、北穂高小屋でアルバイトをしていた息子さんからかねがね「オヤジ、北穂の池は本当にいい所やで」と聞かされていたからだ。
藤本さん自身、北穂高岳に登った際に何度か池を遠望していたが、話を聞いてなおさら憧れは募っていた。その計画をようやく実行に移せたのが、2001(平成13)年9月のことであった。
藤本さんは、高校・大学時代と続けて山岳部に所属。社会人になってからも学生時代の仲間らとともに「より高き山、より困難な山」を志向するオールラウンドな登山を国内外の山で実践してきた。山への意欲は還暦を過ぎても衰えることなく、近年も残雪期の剣岳登山、比良全山縦走、西北ネパールのトレッキングを行なうなど、今なお現役として山登りを楽しんでいる。
9月26日、藤本さんは山岳部時代の後輩ふたりと上高地から入山。涸沢にテントを張った。この時期に計画を立てたのは、念願の北穂池を訪ねると同時に、涸沢の紅葉も愛でようという心積もりがあったからだ。翌27日は天気が下り坂という予報が出ていたため、奥穂を日帰りで往復する予定を変更し、北穂高小屋へと上がった。夕食後には小屋番から北穂池へのルートを教えてもらい、明日の行動に備えた。
28日は、夜来の雨が明け方から雪に変わった。小屋のテラスには2、3cmほどの雪が積もったが、天気予報は「午後から晴れる」と告げていた。
雪は8時ごろにやみ、ただちに3人は行動を開始した。小屋を出たのが8時20分。大キレットへの縦走路を下り、A沢のコルに9時40分到着。ここから一般ルートを外れ、ガレ場を右下方にトラバースしていった。小さな尾根を乗り切ったところで北穂池が見えた。この先、池までは踏み跡もケルンもなく、浮き石だらけのガレ場を行くことになる。そのガレ場を下っているときに、事故は起きた。
「歩いているうちに暑くなってきたので、出発前に着込んでいた冬用のヤッケを脱ごうとしたんです。そのときに立ち止まって脱げばよかったんですけど、歩きながら脱ごうとしたのが失敗でした。先を歩いている後輩と私との距離がどんどん離れていたので、早く追いつかなきゃという焦りがあったもんで……。そうしたらちょうど浮き石の上でバランスを崩して滑落してしまったんです」
その瞬間、「しまった。やってしまった」と思ったという。滑落距離は5mほどだったが、転げ落ちるときに右膝の下に激痛が走った。ハッと我に返ってみると、右膝からかなりの出血があり、靴を赤くぬらしていた。右の肋骨にも痛みがあり、メガネの左のレンズがひび割れていた。すぐに後輩が駆け寄ってきてくれたが、応急手当をしようにもファーストエイドキットを持っていなかった。だが、どうにか歩けそうだったので、そのまま北穂池へと向かった。
大小3つの池からなる北穂池は、思っていたとおりのすばらしいロケーションだった。天気がよければ、池の畔にテントを張り、本でも読みながら2、3日のんびりと過ごしたいところだった。このときもほんとうはゆっくり昼食を食べるつもりでいたが、涸沢まで無事下れるだろうかという不安と膝の痛みから、とにかく先を急ぐことにした。
草付きの嫌なルンゼをどうにか自力で這い上がり、北穂東稜のコルからは斜度60度ほどの岩場をクライミングダウンで慎重に下っていった。
「みんなに迷惑をかけないように、体を騙し騙ししながらという感じで。岩場のクライミングダウンはかなり厳しかったですね。膝の痛みもすっかり忘れていました。でも、ようやく一般コースまで下りたら、緊張が解けたのか体の痛みがひどくなり、ぐったりしてしまいました。で、休み休みしながらなんとか涸沢までたどりついたんです」
涸沢到着は午後3時。事故の発生が11時前だったから、傷を負った体で4時間以上行動したことになる。
傷は右膝の下、横5㎝、縦3㎝ほどの裂傷だった。後輩が涸沢ヒュッテで消毒剤と包帯をもらってきて傷の手当をしてくれた。ふたりは傷の具合を心配していたが、先輩である手前、「まあ、大丈夫だよ。一晩寝れば治るよ」と言って平気を装い、その日は予定どおりテントに泊まった。
だが、寝ている間にも傷の痛みはだんだんとひどくなり、結局、一睡もできないまま朝を迎えた。テントを撤収し、上高地へ下ろうとしたときには、膝の痛みがひどくてほとんど歩くことができない状態だった。
「上高地まではなんとか自力でと思っていたんですけど、ザックは担げても、150mほど離れているヒュッテまで行くのにも這うような有り様だったんです。これじゃあとても自力で下りられないと思い、恥を忍んで救助を要請することにしました」
涸沢ヒュッテを通してヘリコプターの出動を要請し、30分も経たないうちにやって来た民間ヘリに搬送され、藤本さんは無事、豊科赤十字病院に収容された。レントゲン撮影の結果、骨には異常なく、右膝下の傷は6針縫った程度ですんだ。ただ、肋骨の痛みはなかなか引かず、10月20日ごろまで続いた。
事故を振り返って、藤本さんがこう言う。
「事故の原因は、言うまでもなく着ているウェアを歩きながら脱ごうとしたことに尽きます。面倒くさがらずに、足場のいいところで立ち止まって脱ぐべきでした。それを考えると、歩きながら景色に目を奪われたり、おしゃべりに夢中になったりするのも危険だなあと思いました。ほんと、お恥ずかしい話なんですが、私にとってはいい教訓でしたね」
藤本さんが山の大ベテランであることは、山行歴を見れば一目瞭然である。だが、それでも転滑落事故は起こる。ベテランであろうが初心者であろうが関係ない。ちょっとした不注意や油断が命取りになってしまうのが転滑落事故なのだ。
警察庁が毎年発表する山岳遭難事故統計を見ても、事故要因のなかでダントツに多いのが転滑落事故(転倒含む)だ。ちなみに2001年度の統計を見てみると、遭難者総数1470人のうち、滑落・転倒・転落による遭難者は全体の約40%にあたる593人である。しかも転滑落事故の場合、発生場所にもよるが致命傷に至たったり重傷を負ったりするケースが非常に多い。藤本さんが6針を縫うケガだけですんだのは、運がよかったと言っても過言ではない。
繰り返して言うが、転滑落事故の要因は、登山者のひとりひとりの内に潜む不注意や油断にある。ならば転滑落事故を防ぐにはどうしたらいいのか、答えはおのずと出るはずだ。
今、あなたが歩いている登山道で、もし足を滑らせたら、岩につまずいたら、あるいはバランスを崩したらどうなるのか。そのことを常に考えながら、気を引き締めて行動するよう心掛けたいものである。
山と渓谷2003年8月号198ページより